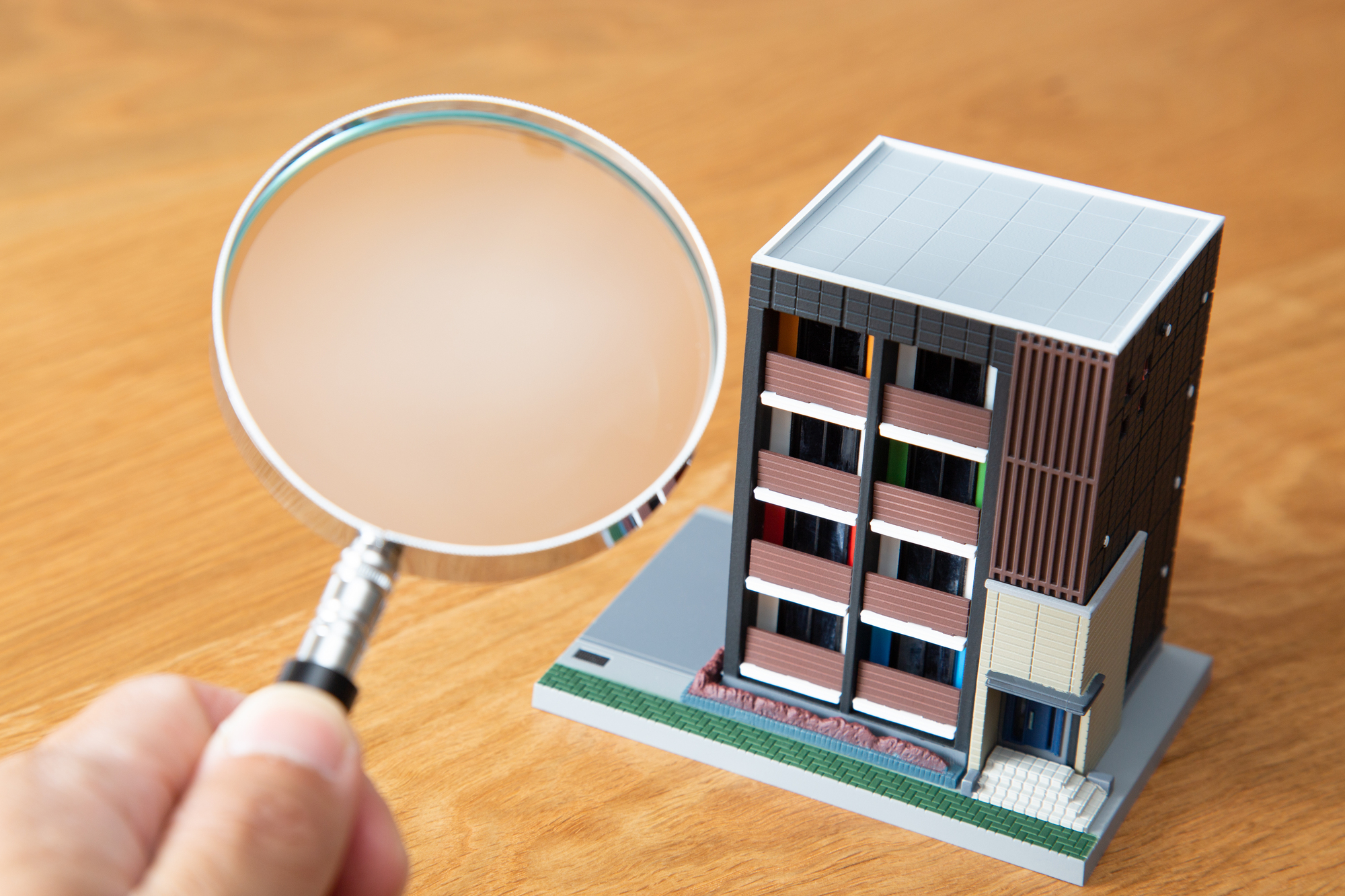
不動産を所有・運用している方の中には、「節税対策として法人化したほうがいいのでは?」と悩んでいる方も少なくありません。相続税対策や所得の増加にともなう税負担の軽減を目的に、法人化を検討するケースは年々増えています。
とはいえ、不動産の法人化には「いくらからするべきか?」という判断基準だけでなく、相続対策としての有効性や、メリット・デメリット、具体的なスキームの把握が欠かせません。
本記事では、不動産の法人化を検討するうえでの目安・節税効果・注意点・手法の違いなどをわかりやすく解説します。相続や資産承継を見据えた最適な判断の参考にしてください。
1. 法人化の前に確認しましょう
不動産の法人化を検討する際は、まず「いつ法人化するべきか」「誰を株主にするべきか」「相続対策として効果的なタイミングはいつか」といった基本的なポイントを押さえることが大切です。これらのポイントを理解すれば、法人化による節税効果や資産承継のメリットを最大限に活用できます。
法人化の判断基準や相続を見据えた準備について詳しく解説します。
1‐1 法人化する目安は所得が900~1,000万円を超えたとき
不動産の法人化を検討する代表的な目安は、課税所得が900万円から1,000万円を超えたタイミングです。
個人の所得税は所得に応じて税率が上がる累進課税制度で、課税所得が900万円を超えると所得税率は33%になります。加えて住民税が約10%かかるため、実際に納める税金の割合はおよそ43%です。
【所得税の税率】
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超330万円以下 | 10% |
| 330万円超695万円以下 | 20% |
| 695万円超900万円以下 | 23% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
一方、法人の場合は法人税や地方法人税、法人住民税、法人事業税などを合わせた実効税率がおよそ35%とされています。
このように、課税所得が900万円を超えると、個人よりも法人の方が税率負担が軽くなりやすく、不動産収益に対して法人で経営した方が有利になるケースが多いです。ただし、法人化にあたっては設立費用なども考慮する必要があり、一般的には課税所得がだいたい1,000万円を超えたあたりが法人化の目安とされています。
例えば、給与所得に加えて不動産所得でも安定した黒字が出ている場合、法人化によって数十万円単位で税負担が軽減される可能性があります。結果として、月々の手取りが増えるケースもあるため、法人化を検討する価値は十分にあるでしょう。
1‐2 株主は相続人にしておく
不動産を法人化する際は、将来的に相続を見据えて株主を子どもなどの相続人にしておくことが効果的です。法人が保有する不動産の資産価値が高くなったとしても、法人株式はすでに相続人が所有しているため、相続税の課税対象とならず、結果として負担を抑えられます。
もし親を株主とした場合、親が亡くなると株式自体が相続財産となり、せっかく法人化して資産を分散させた効果が薄れてしまう恐れがあります。最初から子どもなどを株主にしておけば、このような税負担のリスクを回避しやすくなるでしょう。
さらに、株主を相続人にしておくことは、認知症への備えとしても有効です。万が一、自分が認知症などで意思決定が難しくなった場合でも、相続人である子どもが株主であれば、法人の経営や財産管理を引き継ぎやすくなります。
ただし、株式の評価方法や相続税の計算は専門的で複雑です。相続対策として効果的に機能させるには、税理士など専門家のサポートを受けながら、早めに体制を整えておくことが重要です。
2.メリットを確認しましょう
不動産を法人化すると、相続税や贈与税の節税に加えて、資産のスムーズな移転や遺産分割のしやすさといった、個人所有では得られにくいメリットが生まれます。特に将来的な相続や資産承継を見据えている方にとっては、法人化が有効な選択肢となるでしょう。
不動産の法人化によって得られる代表的なメリットを、3つの視点からわかりやすく解説します。
2‐1 相続人への相続税や贈与税を節税できる
不動産を法人化すると、相続税や贈与税の負担を軽減できる可能性があります。法人が不動産を所有している場合、相続の対象となるのは物件そのものではなく、法人の「株式」です。株式は、相続税評価額の計算において、不動産を個人で所有している場合よりも低い金額で評価されるケースが多く、結果的に相続税の節税につながります。
また、不動産から得られる賃料収入も法人に帰属するため、個人に資産が蓄積されにくくなります。そのため、相続時の課税対象となる財産そのものを抑えることができることも大きなメリットです。
このように、法人化によって不動産と収益を法人に移すことで、相続税の節税効果が期待できるのです。
2‐2 役員報酬や退職金として資産を移転できる
不動産を法人化すると、自分や家族を役員にして、役員報酬や退職金という形で資産を計画的に移転しやすくなります。
役員報酬は法人の経費として計上できるため、法人税の節税効果が期待できます。また、退職金には一定の要件を満たせば所得税の軽減措置もあり、将来的な資産移動に役立つ手段です。
個人事業では給与という概念がないため、基本的に代表者や家族への報酬を経費にできませんが法人化によって可能になります。さらに、家族への給与や退職金も法人の経費にできるため、税務上のメリットが増えます。家族経営の体制を整えつつ、資産を円滑に次世代へ引き継げる点は大きな利点といえるでしょう。
2-3 遺産分割が容易になる
個人で不動産を所有している場合、相続時の遺産分割が難航することが少なくありません。物理的に分割できない不動産は、相続人間で不公平感やトラブルの原因となりやすいためです。
しかし、不動産を法人化すれば、資産は「株式」として分割可能な形になります。例えば、600株の株式を3人の相続人に200株ずつ分けることができるため、遺産分割の自由度が大きく高まります。 ただし、株式が分散するため決議が遅延したり、停滞したりするリスクが高まります。その結果、会社の方針が決定しづらくなるため、注意が必要です。
また、法人化により相続発生後の手続きも簡略化されます。個人所有の場合、家賃振込先の変更や契約の名義変更など複雑な手続きが必要ですが、法人名義の口座や契約がすでにあるため、こうした作業がスムーズに進み、相続人の負担を軽減できるでしょう。
このように、法人化は遺産分割を容易にし、相続人間のトラブル防止や手続きの簡便化にもつながる有効な選択肢です。
3.デメリットを確認しましょう
不動産の法人化には多くのメリットがありますが、その一方でデメリットや注意するべき点も存在します。法人化は一度行うと元に戻すことが難しく、運用や税務処理も個人所有とは大きく異なるため、慎重な判断が必要です。
不動産を法人で所有・運用する際に想定される主なデメリットについて解説します。導入前にしっかりと理解しておきましょう。
3‐1 法人を設立する際に費用と手間がかかる
不動産を法人化するには、まず法人を設立する必要があります。その際には、登録免許税や定款認証費用、専門家への報酬など、一定の初期費用が発生します。さらに、登記手続きや銀行口座の開設、各種届出などの事務作業も多く、慣れていない人にとっては負担に感じやすいでしょう。
また、個人所有の不動産を法人名義に移す場合、不動産取得税や登録免許税、譲渡所得税などの移転コストも発生します。これらの金額は物件の規模や状況によって異なるため、事前にシミュレーションしておくことが重要です。
さらに法人化後も、毎年の決算・税務申告、社会保険手続きなど、個人所有では発生しなかった事務処理が必要になります。これらを専門家に依頼する場合は、顧問料などの継続的な運営コストがかかる点にも注意が必要です。
このように、法人化には節税や相続対策といったメリットがある一方で、設立や維持にかかる費用・手間も無視できません。長期的な視点でトータルコストを把握し、慎重に判断することが大切です。
3‐2 長期所有の場合、売却時に税率が高くなる
個人が不動産を所有している場合、所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」となり、所得税・住民税の税率が軽減されます。具体的には、長期譲渡所得の税率は合計20%程度に抑えられます。
一方、法人が不動産を売却すると利益は法人の事業所得として課税され、所有期間に関わらず法人税率(中小企業であれば15~23.2%)が適用されます。つまり、長期保有による軽減措置がないため、売却時の税負担が個人所有の場合より重くなる可能性があるのです。
そのため、特に長期間保有した不動産を売却する予定がある場合は、法人化による税負担の違いを十分に検討する必要があります。
3-3 従業員の社会保険料を負担しなければならない
法人になると、実質的に家族経営であっても、役員や従業員には社会保険への加入が義務づけられます。役員報酬を支給する場合、報酬額に応じた社会保険料を法人と個人の双方で折半する必要があります。
こうした負担は、売上が安定していない初期の段階では、特に重くのしかかる可能性があるでしょう。また、配偶者や子どもに役員報酬を支払うなど、節税目的の体制であっても、保険料の負担が増える点には注意が必要です。
一方、個人事業として運営している場合は、常時使用する従業員が5人未満であれば、社会保険への加入は義務ではありません。同じ規模・体制であっても、法人化によってコスト構造が大きく変化する点は理解しておく必要があります。
3-4 赤字経営でも法人住民税が発生する
法人は赤字であっても、「均等割」と呼ばれる法人住民税の支払いが毎年発生します。均等割は、資本金や従業員数に応じて定められており、最も低い区分でも年間7万円(都道府県民税と市町村民税の合計)を納めなければなりません。つまり、利益の有無にかかわらず固定的に課税される仕組みです。
一方、個人事業主の場合、所得がゼロであれば所得税や住民税が課税されないのが一般的です。赤字でも納税が必要になる点は、法人と個人との大きな違いといえるでしょう。
資金繰りが厳しい時期や、小規模な経営体においては、こうした固定費の存在が重荷となる可能性もあります。法人化を検討する際には、税務面での継続的なコストも視野に入れて計画を立てることが重要です。
4. 不動産を法人化する方法は3つあります
不動産を法人化する方法には、大きく分けて3つのスキームがあります。所有形態や課税関係、管理の手間などに違いがあるため、目的や状況に応じて適切に選ぶことが大切です。
不動産法人化の代表的な3つの方法について、それぞれの特徴と注意点をわかりやすく解説します。
4‐1 不動産所有方式
不動産所有方式は、個人が所有している不動産を法人に移転し、法人名義で保有・運用する方法です。移転の方法としては、売却または現物出資などがあり、いずれも法人が不動産の所有権を取得します。家賃収入などの事業収益はすべて法人の所得として計上されます。
不動産所有方式の大きなメリットは、収益が法人に帰属するため、所得分散や相続対策の選択肢が広がる点です。法人の経費計上が可能になるため、税務上の柔軟性も高まります。
一方で、個人から法人に不動産を移転する際には「譲渡所得税」「登録免許税」「不動産取得税」などの初期コストが発生します。特に土地の移転については、課税リスクが高くなるため、建物のみを法人名義にするケースも少なくありません。
4‐2 管理委託方式
管理委託方式は、不動産の所有権を個人に残したまま、契約事務や維持管理といった管理業務のみを法人に任せる方法です。法人は対価として管理料を受け取り、利益を得る仕組みです。管理料の相場は一般的に賃料の4~6%程度とされ、市場水準に見合った適正な設定が求められます。
管理委託方式は所有権の移転が不要なため、登記や譲渡所得税など、法人化にともなう手続きや税負担を軽減できる点がメリットです。相続時には個人所有の不動産として扱われるため、小規模宅地等の特例が適用されやすくなる可能性もあります。
ただし、法人に支払う管理料が実態より過大であると、税務上「実質的な所得移転」と判断されるリスクがあります。節税効果を得るには、契約内容の妥当性や管理料の水準が適正であることが重要です。
4‐3 サブリース方式
サブリース方式は、個人が所有する不動産を法人に一括で貸し出し、法人が物件を第三者に転貸する仕組みです。法人は転貸によって得た賃料から、個人オーナーに支払う賃料(保証賃料)を差し引いた金額を利益とします。一般的に、オーナーに支払われる保証賃料は家賃の85~90%程度とされており、家賃の10~15%程度が法人の取り分となるのが相場です。
サブリース方式も管理委託方式と同様に、不動産の所有権を個人に残したまま法人を活用できる点が特徴です。不動産の所有権を移転する手続きが不要なため、法人化にかかる初期費用や手間を抑えられるほか、相続対策として段階的に法人を活用したい方にも適しているでしょう。
一方で、サブリース契約には注意点もあります。法人が転貸を行う場合は、入居者との賃貸契約を法人名義で締結する必要があるため、すでに入居者がいる物件では契約の切り替えなどの手続きが発生します。また、保証賃料の水準や契約条件によっては収益性が左右されるため、契約内容の精査と適切な設計が不可欠です。
5.まとめ
不動産の法人化は、相続税の対策や高所得者層における節税手段として、有効な選択肢のひとつです。年間所得が900~1,000万円を超えるケースや、将来的な資産承継を見据える場合には、導入を検討する価値があるでしょう。
ただし、法人設立や運営にかかるコスト、税制上の制限など、留意するべき点も少なくありません。メリットとデメリットをきちんと把握したうえで、慎重に判断することが重要です。
また、不動産法人化には「所有方式」「管理委託方式」「サブリース方式」など複数の方法があり、それぞれに適した使い方があります。相続や資産運用の将来計画を踏まえ、税理士などの専門家と相談しながら、長期的な視点で最適な方法を選びましょう。
ご不明な点等ございましたら、ランドマーク税理士法人にお問い合わせください。






 なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。 無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。



















