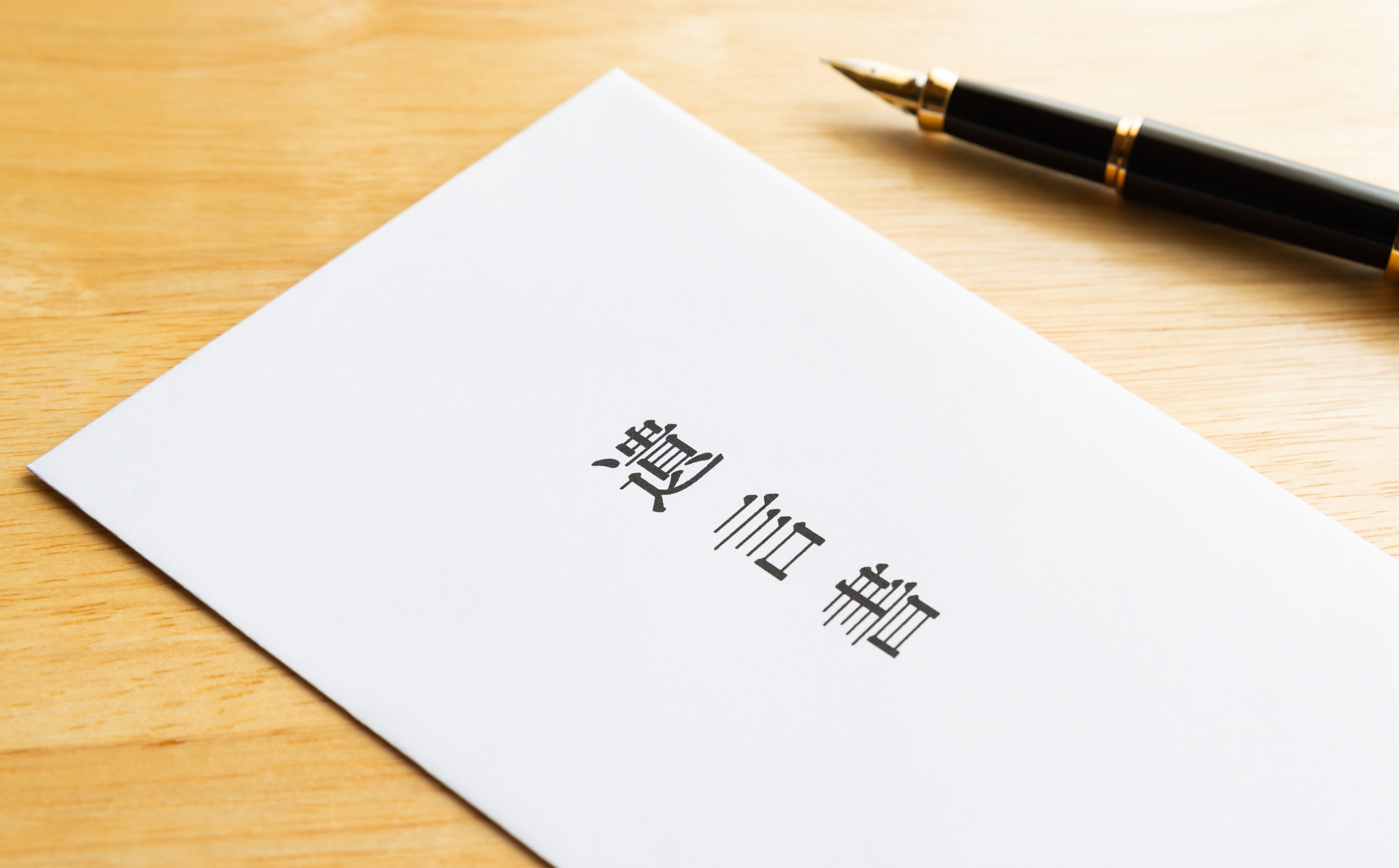
遺言書を作成した人が亡くなった場合、相続人はどのような手続きを取れば良いでしょうか。
遺言書が見つかった場合は、遺言書に書かれた内容に従って相続の手続きを行います。
遺言書は大きく分けて3つの種類があり、それぞれの遺言書によって手続きの進め方も違いがあります。
そこで今回は、遺言書が見つかった場合の相続の手続きについて解説いたします。
<今回の記事でわかること>
- 遺言書の種類とそれぞれの特徴
- 遺言書がある場合の相続手続きの流れ
- 遺言書がある場合の注意点
遺言書を作成している遺族がいらっしゃる方や、これから遺言書を作成しようとしている方はぜひ最後までご覧ください。
1. 遺言書がある場合の相続手続きについて確認しましょう
遺言書が見つかった場合、遺言書の内容によって手続きの仕方が変わってくる点に注意しなければなりません。
基本的に、遺言書が見つかった場合は、遺言書に書かれた内容に従って相続をしていきます。
遺言書には、主に3つの種類があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれの遺言書によって作成や保存方法も違いがあり、特徴も違います。
また、遺言書の種類によって手続きにも違いが出てくるので、気をつけてください。
ここからは、遺言書の種類について詳しく解説していきます。
2. 遺言書には種類が3つあります
遺言書は3つの種類があり、それぞれに特徴やメリットとデメリットがあります。
最初に3つの遺言書について詳しく解説していきます。
まずは、簡単に3つの遺言書の特徴を表にまとめました。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 証人 | 2名以上 | 不要 | 2名以上 |
| 保管方法 | 公証役場 | 本人が保管 | 本人が保管 |
| 作成方法 | 本人が口述し、公証人が遺言書を作成する | 本人が自筆で遺言書を作成し、押印する | 本人が遺言書を作成し、封筒に入れ封をして公証役場に持参する |
| メリット |
|
|
|
| デメリット |
|
|
|
2-1. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人が立ち合いのもと公証人が遺言書を作成します。
作成する時は、遺言者と公証人の他、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。
なお、証人の対象となる人は、相続人や相続人の関係者、公証人の関係者、未成年者など利害関係者以外の人です。
証人は、友人等に頼める人がいる場合は頼んでみましょう。
身近に依頼する人がいない場合は、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。
公正証書遺言の作成方法は、本人が口述し、公証人が作成します。
このため、公証役場まで出向く必要があります。
もし、病気や怪我などで入院していたり、施設に入っていて公証役場まで出向くことができなかったりする場合は、公証人が出張で出向くことも可能です。
その場合は、別途費用がかかるので気をつけましょう。
次は、公正証書遺言のメリットとデメリットについて解説します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、大きくあげて次の2つになります。
- 公証人を通じて遺言書を作成するため安全性が高い
- 不備が起こりにくい
公正証書遺言のメリットは、公証人を通じて遺言書を作成するため、安全性が高い点です。
また、遺言書の紛失や改ざんなどもできないため、安心して保管しておくことができます。
その他、遺言者は口述し、公証人が文章でまとめるため、形式不備となることもありません。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは次の2つです。
- 費用がかかる
- 公証人を通して遺言書を作成するため、手間がかかる
公正証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて費用がかかることです。
公正証書遺言の作成費用は、財産金額によって違うため、財産が高くなると費用も高くなってしまいます。
特に証人2人以上に立ち会ってもらう場合に、行政書士や司法書士など専門家にお願いすることで、さらに費用がかかってしまいます。
これらの点から、公正証書遺言を作成する場合は、ある程度の費用をみておく必要があります。
デメリットの2つ目は公証人を通して遺言書を作成するため、手間がかかる点です。
先ほどご紹介した通り、公正証書遺言は、人の力を借りて遺言書を作成します。
また、公証役場まで出向かなければならないため、時間や手間がかかります。
2-2. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言書を作成する遺言書です。
いつでもどこでも気軽に書くことができるため、自分のタイミングで遺言書を作成できます。
自筆証書遺言は、公正証書遺言のように費用がかからないため、コストを抑えたい人にはおすすめの遺言書となっています。
保管方法も自宅や信頼できる親族や友人に預けることや、銀行などの貸金庫に保管することもできます。
一方で、紛失してしまったり、遺言者が亡くなった後に見つけられなかったりなどのリスクもあります。
このようなリスクを避けるために、法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言保管制度」を利用する人もいます。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、気軽に遺言書が書ける点です。
公正証書遺言のように公証役場に出向いたり、そのための時間を作ったりすることもないため、自分のペースで遺言書を作ることができます。
また、書き直しも好きなタイミングで書き直すことができます。
その他にも自筆証書遺言のメリットとして、費用があまりかからない点も挙げられます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、自分で遺言書を書くため、不備があると無効になってしまう点です。
例えば、作成日の書き忘れや代筆、パソコンでの作成などは遺言書としての効力が無くなってしまいます。
他にも、保管先を自宅にしていることで、見つかった後に誰かに隠蔽されたり、破棄されたりといったリスクもあります。
2-3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言の特徴は、遺言書の内容を秘密にしたまま、存在を公証人に証明してもらう遺言書です。
秘密証書遺言は、誰にも遺言書の内容を知られたくないという人にはおすすめの遺言書になります。
遺言書を作成後、封筒に遺言書を入れて封をしたものを公証人に見せる形で保管します。
保管先は、自宅や知人に預けることや、貸金庫などになります。
また、秘密証書遺言はパソコンや代筆による作成も可能です。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言者が遺言の内容を秘密にできる点です。
このため、改ざんや偽造などをされる可能性が低く、安心して遺言書を残すことができます。
遺言書の作成方法は、代筆やパソコンが可能であり、自分で署名と押印をするだけで良い点も挙げられます。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットは、遺言書が無効になりやすい点です。
理由は、遺言書の内容を知っている人は本人しかいないためです。
公証人が遺言書の内容を確認しているわけではないため、いざ封を開けて、遺言書の内容に法律的な不備があった場合は無効になってしまいます。
この他にも、秘密証書遺言は、公証人手数料などの費用がかかる点もデメリットとしてあげられます。
2-4. 遺言書を発見した時は開けていい?
故人がなくなり、遺品整理などをしているときに遺言書を発見することがあるかもしれません。
そのときに遺言書を開封しても良いのかと疑問に持たれる方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、遺言書を発見した時は勝手に開封してはいけません。
速やかに遺産分割を行う必要があります。
遺言書を発見した場合は、遺言書の種類によって「検認」手続きを行います。
もし、勝手に開封などしてしまうと、法律違反となり5万円以下の過料を課せられますので注意しましょう。
3. 遺言書がある時の相続手続きの流れ
ここからは、遺言書が発見された時の相続手続きの流れについて解説します。
大きく分けて次の流れになります。
- 遺言書の調査
- 自筆・秘密証書遺言の場合は検認の手続きが必要
- 相続人や相続財産の調査
- 相続税の申告や相続登記を行う
一つずつ取り上げて解説します。
3-1. 遺言書の調査
遺品整理などで遺言書を発見したら、遺言書を調査しましょう。
遺言書の種類がどの形式のものであるかを確認する必要があります。
また、封印してある遺言書は家庭裁判所で相続人立ち合いのもと開封しなければなりません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に持っていきましょう。
そして、「検認」を行う必要があります。
3-2. 自筆・秘密証書遺言の場合は検認の手続きが必要です
見つけた遺言書を家庭裁判所に持ち込んだら検認の手続きが必要になります。
検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、正しい相続を行うことです。
検認することによって、偽造や隠蔽を避けることができます。
検認しなかった場合、遺言書の効力が消えるわけではありませんが、検認を行っていない遺言書は、金融機関などの相続手続きが拒否されることがあります。
そのようなトラブルにならないためにも検認の手続きはしておいた方が良いでしょう。
3-3. 相続人や相続財産の調査
遺言書が見つかったら、遺言書に書かれている内容の通りに相続財産の分割を行う必要があります。
誰が相続人となり、相続財産をどのように分割するのかを確認した上で、相続手続きを行うようにしましょう。
また、遺言書から遺言執行者が指定されている場合もあります。
その場合は、遺言執行者が手続きを行うことになります。
手続きに不安を持たれる方や、やり方がよくわからないという方は専門家に依頼することを検討しましょう。
3-4. 相続税の申告や相続登記を行う
相続財産が決定したら、相続税の申告や相続登記を行う必要があります。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
一方、不動産などの相続登記は原則3年以内と期限が決められています。
どちらも期限が定められているため、早めの手続きを行うようにしましょう。
特に、相続税は、期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税といった余分な税金がかかってしまうことがあります。
税金を多く払わないためにも申告期限は守るようにしましょう。
相続税の申告や相続登記のやり方がわからない方や、手続きに不安を抱えている人は、専門家に依頼することも検討しましょう。
4. 注意点
遺言書が見つかった時の注意点についてご紹介します。
遺言書が発見された場合に注意する点は次の3つになります。
- 遺言書が複数存在する場合:最新のものが有効
- 遺産分割協議後に遺言書が発見された場合:遺言書が優先
- 遺言書と異なる遺産分割を行う場合には条件があります
4-1. 遺言書が複数存在する場合:最新のものが有効
複数の遺言書が発見された場合は、最新のものが有効となります。
原則として、日付が一番新しい遺言書が効力を発揮しており、有効なものとして取り扱われます。
遺言書は何度も書き直しができるため、古い遺言書は効力がないと見なされるのです。
4-2. 遺産分割協議後に遺言書が発見された場合:遺言書が優先
遺産分割協議後に遺言書が発見された場合は、遺言書に書かれた内容が優先となります。
遺言書は、被相続人の意思が書かれた書類であり、その意思を尊重しなければなりません。
そのため、例え遺産分割協議が終わっていたとしても、遺言書に書かれた内容の通りに遺産分割をしなければならないのです。
ただし、遺産分割協議後で遺言書が発見されたとしても、既に分割協議で相続人全員の合意がある場合は、従前の遺産分割内容で手続きを行うことが可能です。
その場合は、相続人全員が遺言書の存在や内容を知った上で合意をとる必要が出てきます。
4-3. 遺言書と異なる遺産分割を行う場合には条件があります
原則、遺言書が発見された場合は、遺言書に書かれた内容通りに遺産分割をする必要がありますが、異なる遺産分割を行うことも可能です。
しかし、一定の条件を通過しないと遺言書の内容と異なる遺産分割はできません。
遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合は、相続人全員の合意が必要になります。
また、遺贈を受けている人がいる場合でも、受贈者全員からの合意が必要です。
加えて、遺言執行者が指定されている場合も遺言執行者からの同意も必要になります。
遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは、数多くの手続きを強いられることとなるため、専門家と相談して手続きを進めることをお勧めします。
5. まとめ
今回は、遺言書が見つかった時の発生後の手続きについて解説してきました。
遺言書には、3つの種類があり、それぞれに保管先や手続き方法などが異なります。
また、種類によって費用も違いが出るため、遺言書を作成する際は、どの方法がご自分に合うかどうかを考えてから作成することをお勧めします。
故人が亡くなった後に遺言書を見つけた際は、勝手に遺言書を開けることはできません。
速やかに遺言書の調査を行い、検認などの手続きを行いましょう。
遺言書が発見されて、手続き等に不安を感じる方は、ランドマーク税理士法人にご相談ください。






 なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。 無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。



















