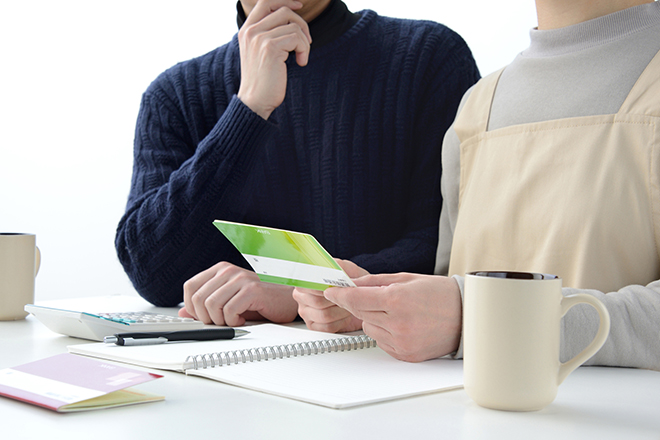
相続税は、相続財産を取得した人(相続人)が、取得した財産の価額に合わせて計算された金額を納める税金です。
相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされており、期限に間に合わなかった場合は、延滞税などの追加の税金を支払うことになります。
これは、相続人になった人全員が対象となりますが、中には期限内に納付しない人も出てくるかもしれません。
その場合、「連帯納付義務」として、各相続人が連帯して相続税を納付しなくてはなりません。
相続税の連帯納付義務によって相続人同士がトラブルになるケースもあります。
そこで今回は、相続税の連帯納付義務について詳しく解説します。
また、他の相続人が納付しないときの責任や対応策などについても徹底解説していきます。
相続税は、自分が払ってしまえば終わりというわけではありません。
この記事を通じて、相続税の連帯納付義務についての理解と対策をすることで、トラブルに巻き込まれないための心構えなどを身につけることができます。
ぜひ最後までご覧ください。
1.相続人が複数人いる場合は連帯納付義務があります
相続税は、相続人が複数人いる場合、連帯納付義務があります。
連帯納付義務とは、亡くなった人の財産に対して課される相続税を完納するまで各相続人がお互いに連帯して納付しなければならないというルールです。
例えば、被相続人である父から長男と次男に相続税が発生した場合の例を見てみましょう。
仮に長男が納付しなければ、次男が長男の納付すべき金額を払わなくてはいけなくなってしまうというルールなのです。
ここでは、連帯納付義務について詳しく解説していきます。
1-1 連帯納付義務を負う人
相続税の連帯納付義務を負う人は、同じ被相続人から財産を受け取った全ての人が対象となります。
亡くなった方の法定相続人になる人はもちろんですが、遺言により財産を受け取った受遺者、死亡保険金を受け取った人も対象です。
さらに、その被相続人から生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用している方がいる場合も対象となるので気をつけましょう。
ただし、相続放棄をしている人は対象にはなりません。
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も含めて、財産を引き継ぐことを放棄することです。
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要になり、原則、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならないため、注意しましょう。
1-2 自分の相続税を既に支払っていても連帯納付義務がある
連帯納付義務は、自分の相続税を既に支払っている場合でも、連帯納付義務が発生します。
たとえ、既に納付していたとしても、他の人が相続税を納付していない場合は、税務署から「納付通知書」が送付されてしまうのです。
そのため、できる限り、相続人同士が協力して相続税をきちんと納めることが大切です。
1-3 連帯納付義務で支払う限度額と時効
相続税の連帯納付義務は、限度額が設けられています。
相続税の連帯納付義務は、それぞれが相続で受け取った財産に関わらず、相続人全員が平等に負担しなければなりません。
そのため、連帯納付義務の納税額は、相続または遺贈により取得した金額が限度額となります。
限度額は以下の通りです。
- 連帯納付義務の限度額=相続した遺産額-納付済の相続税額
つまり、相続で得た利益を限度額とし、既に納付済の相続税を引いたものが連帯納付義務の限度額となるのです。
また、連帯納付義務の時効も定められており、相続税の申告期限から5年となっています。
2.連帯納付義務の流れを確認しましょう
次に連帯納付義務の流れを確認していきましょう。
連帯納付義務者への通知は、「すぐに納付してください」という連絡ではないため、焦る必要はありません。
この流れを知っておくことで、いざ連帯納付義務で納付しなければならなくなった時に焦る必要もなくなり、何をしておけば良いかなど事前の対策もわかってきます。
はじめに全体の流れを解説します。
- 他の相続人が相続税を滞納する
- 税務署から連帯納付義務者に「完納されていない旨等のお知らせ」通知が届く
- 「納付通知書」が届く
一つずつ解説していきます。
2-1 他の相続人が相続税を滞納する
相続税は納付期限が定められており、通常、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
そのため、10ヶ月を過ぎても相続税が納められていない場合は、まず納税者本人に催促状が届きます。
通常、催促状は相続税の納付期限後50日以内に送られます。
それでも滞納している場合は、滞納している人の財産を差押え、その財産を公売にかけて滞納している相続税を納める流れになります。
この時点で相続税を完納できれば何事もなく終わるのですが、まだ納めるべき金額が残っている場合、連帯納付義務が発生することがあります。
2-2 税務署から連帯納付義務者に「完納されていない旨等のお知らせ」が届く
一方で、相続税を滞納している人がいる場合、税務署から連帯納付義務者に通知が届きます。
相続税を滞納している人への催促状が送られてから1ヶ月経っても滞納している場合は、連帯納付義務者に向けて「完納されていない旨等のお知らせ」が届きます。
この通知は「相続人の中にまだ相続税を納付していない人がいます」というお知らせに過ぎません。
既に納付している人に請求しているわけではありませんので焦る必要はありません。
この時点で、もし、滞納者に連絡が取れるのであれば、相続税の納税について解決策を提案することをお勧めします。
2-3 「納付通知書」が届く
それでもなお、相続税を滞納している場合、連帯納付義務者に「納付通知書」が届きます。
「納付通知書」は、納付額や納付期限が明記されており、内容通りの納付額を期限内に納める必要があります。
「納付通知書」に記された納付期限内に納付しないと、延滞税や利子税などがかかりますので注意しましょう。
3.連帯納付義務の注意点を確認しましょう
続いて、連帯納付義務の注意点についてご説明します。
連帯納付義務について注意すべきことを抑えておくことで、実際に連帯納付義務が発生した時の対処に役立ちます。
注意すべき点は次の3点です。
- 納付期限を過ぎた場合は利子税・延滞税が課される
- 連帯納付義務の場合は延納や物納は不可能
- 相続税を肩代わりした場合
一つずつ解説していきます。
3-1 納付期限を過ぎた場合は利子税・延滞税が課される
連帯納付義務が発生し、納付期限を過ぎた場合は利子税・延滞税が課されます。
そのため、連帯納付義務の「納付通知書」が届いた際は、できる限り早めに納付することをお勧めします。
利子税とは、相続税の分割などの延滞により課される利息のようなものです。
連帯納付義務の場合は、催促状が届いてから、未納分の相続税に対して遅れた日数分が計算されて請求されます。
また、納付期限日から2ヶ月をすぎると延滞税も課されてしまいます。
これらのことから、連帯納付義務が発生したら、早めに納付するようにしましょう。
3-2 連帯納付義務の場合は延納や物納は不可能
連帯納付義務では、延納や物納は不可能です。
そのため、連帯納付義務者に対して納付書が送られた場合は、現金で納付することが必須です。
連帯納付義務が発生する原因は、元々相続税の納付義務者の滞納が原因であり、支払期日が過ぎている状態です。
延納や物納は、期限内に申請することが原則のため、連帯納付義務においての延納や物納は認められていないのです。
3-3 相続税を肩代わりした場合
相続税を肩代わりした場合も注意が必要です。
例えば、本来の納付義務者に対して温情があって、相続税を肩代わりした場合などが挙げられます。
相続税を肩代わりした場合にどのような注意が必要なのかを解説していきます。
3-3-1 贈与税がかかる可能性がある
連帯納付義務者が相続税の納付義務者の代わりに相続税を支払うことは、連帯納付義務とは認められません。
もしも、連帯納付義務者が相続税の納付を肩代わりした場合は、贈与したとみなされ、贈与税が新たに発生してしまうこともあるので、注意しましょう。
贈与と認められた場合、余分に税金を納めることになってしまいます。
3-3-2 求償権がある
連帯納付義務者が納付義務者の代わりに相続税を支払った場合、納付義務者に求償権を請求することができます。
求償権とは、税金を肩代わりした連帯納付義務者が本来の納付義務者に対して支払った分を請求できる権利です。
連帯納付義務者が求償権を請求する場合は、次のことに注意しましょう。
- 納付書の控えや通知書などの書類を全て保管しておくこと
- 内容証明郵便を使って納付義務者に請求すること
- 求償権の時効は10年であること
4.連帯納付義務を未然に防ぐ方法を検討しましょう
最後に、連帯納付義務を未然に防ぐ方法について解説していきます。
相続が発生した場合、相続人は期限内に相続税を納めなければなりません。
また、相続税は現金で一括納付することが原則です。
しかし、相続税の金額によっては、高額になってしまうこともあり、一括納付できなくて困ってしまうことも考えられます。
納付期限に間に合わずに滞納してしまうと、他の相続人に迷惑をかけることになってしまいます。
そうした事態を防ぐためには、前もって対策を取ることや、仮に連帯納付義務者に請求が発生してしまった場合にどのように対応するべきかを検討しておくことが大切です。
ここからは、連帯納付義務によって困ることがないよう、未然に防ぐ方法について次の3つをご説明します。
- 延納や物納などの支払い方法があることを確認しておく
- 申告期限を過ぎないように遺産分割について早めに話し合う
- 納税することが難しい場合は、他の相続人が納付を肩代わりすることも検討する
4-1延納や物納などの支払い方法があることを確認しておく
連帯納付義務を未然に防ぐ方法として、延納や物納などの支払い方法があることを確認しておくことが大切です。
延納とは、相続税を現金で納付できない場合に、分割による納付が認められる制度のことです。
しかし、延納は誰でも簡単に変更できるわけではなく、ある程度の条件が必要になるほか、延納をした場合は、利子税もかかることを考慮しておかなければなりません。
延納の条件としては、次の4つが挙げられます。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 納付期限までに金銭で一括納付ができないこと
- 申告期限までに必要な書類を税務署に提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
これらの条件が揃って初めて延納することができます。
一方、物納は、現金以外の財産を相続税として納付することです。
現金以外の財産として挙げられるものは、土地や国債、非上場株式などがあります。
延納が難しい場合は、物納によって相続税を納付できる場合もありますので、検討しましょう。
4-2 申告期限を過ぎないように遺産分割について早めに話し合う
相続が発生した場合、申告・納付期限までに遺産分割について早めに話し合うことが大切です。
相続税の申告や納付は、原則、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
そのため、相続が開始されてから早めに相続人同士での話し合いを行い、遺産分割を円滑に進めるようにしましょう。
遺産分割の段階で、どのくらいの相続税の納付額が発生するのかが分かりますので、納付期限日までに納付義務者同士で納付できるかを確認しておくことも大切です。
4-3 納税することが難しい場合は他の相続人が納付を肩代わりすることも検討する
相続税の納付額が決まったら、期限内に納付することが大切ですが、もしも納税するのが難しい場合は、他の相続人が納付を肩代わりすることを検討してみても良いでしょう。
また、この場合、連帯納付義務者は求償権を使って、本来の納付義務者に請求することができます。
本来納付すべき納税義務者は、肩代わりしてくれた連帯納付義務者への返済計画をしっかりと立てておくようにしましょう。
まとめ
今回は、相続税の連帯納付義務について解説してきました。
連帯納付義務とは、他の相続人が期限内に相続税を納めなかった場合、連帯して税金を納めなければならない制度です。
連帯納付義務者となった場合は、速やかに納付するようにしましょう。
連帯納付義務者にも納付期限が設けられているため、納付できなかった場合は、利子税や延滞税がかかることもあります。
連帯納付義務が発生しないようにするためには、相続人同士での事前の話し合いが必要です。
相続税の支払いトラブルを避けるためには、税理士などの専門分野を得意としている人に相談しておくことがお勧めです。
なにかお困りのことがございましたら、お気軽にランドマーク税理士法人までご相談ください。






 なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。 無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。



















